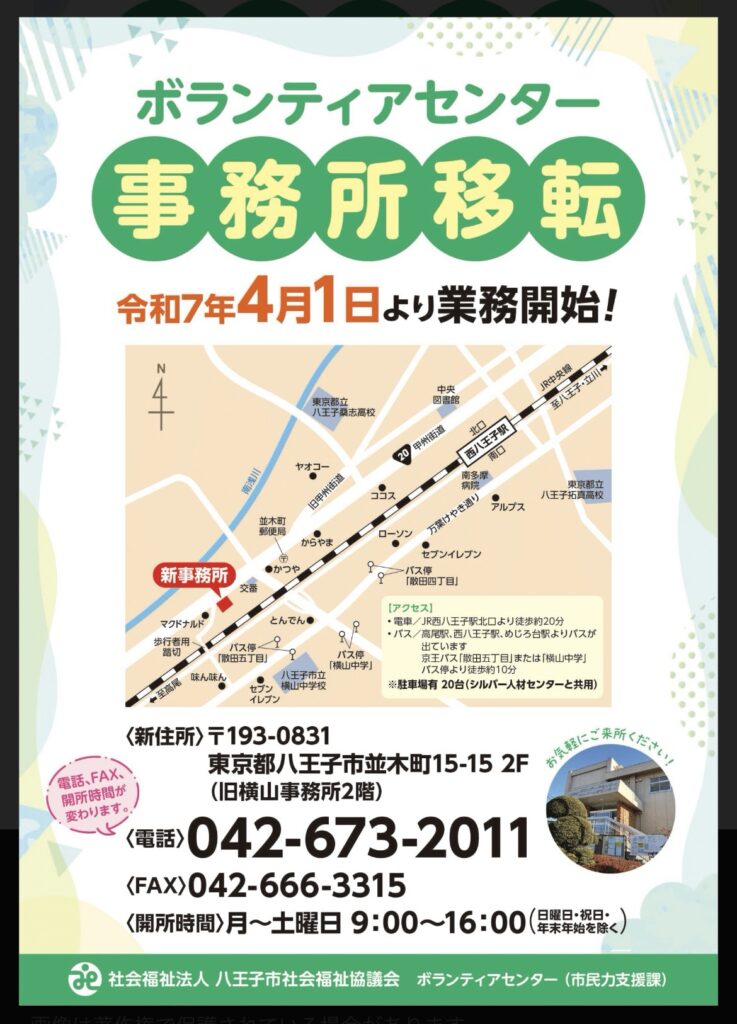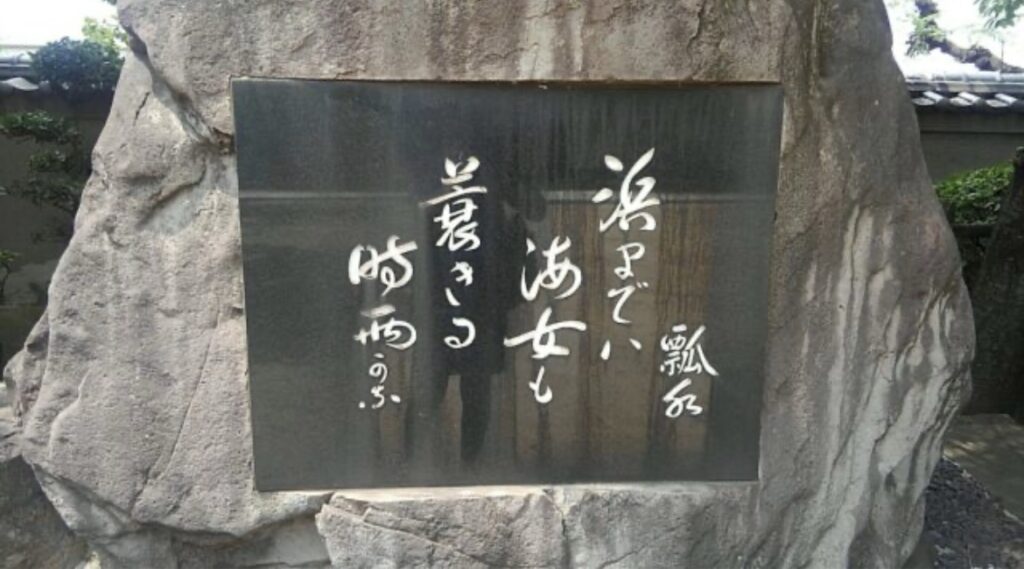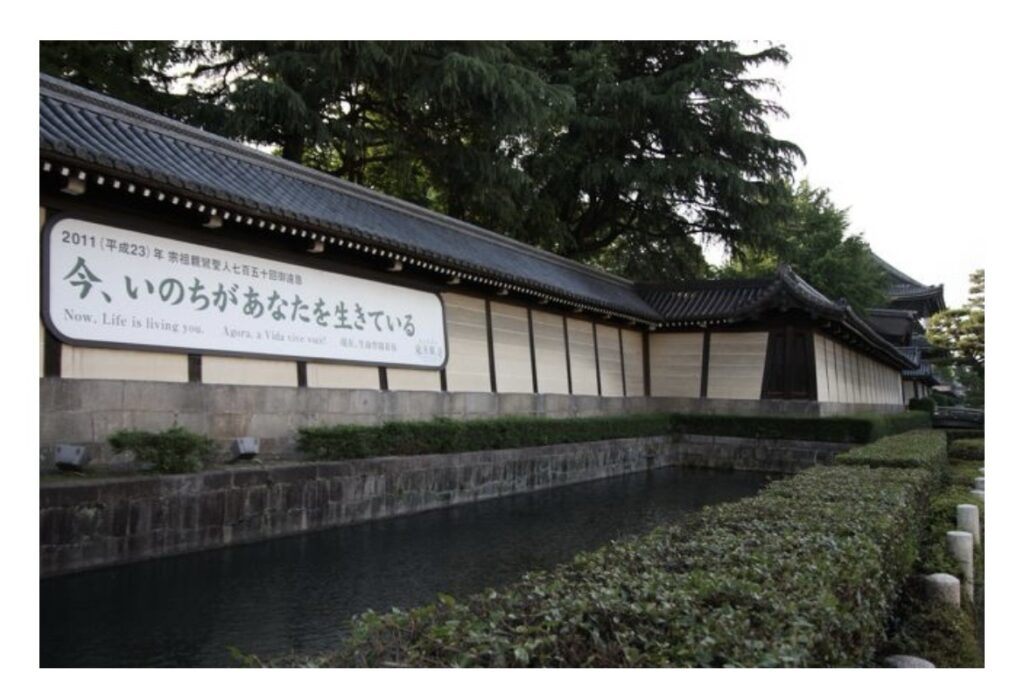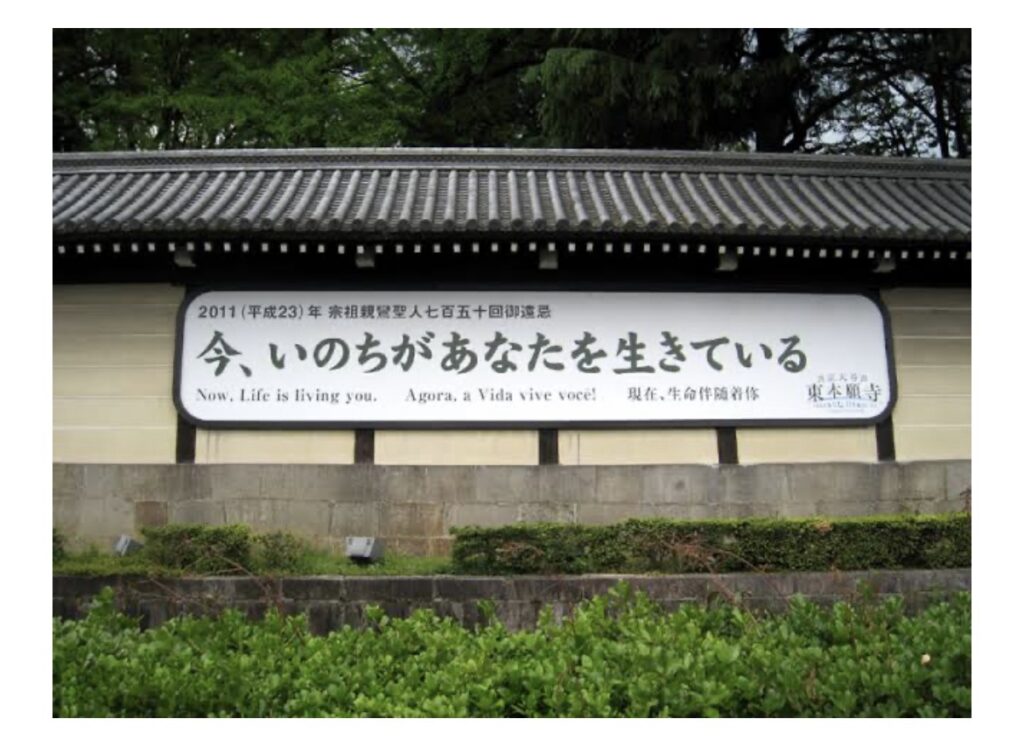先日、地元の小学校の子どもたちがお寺に来てくれた。地域の気になる場所をいくつかピックアップし、グループに分かれてその場所を訪ねる、「町たんけん」授業だ。お寺の由緒や歴史から始まり、普段どんなことをしているのかといった質問を受けながら楽しいひと時を過ごした。
子どもたちからの色々な問いに答えているうちに、本山の修練で教わった金子大栄先生による住職の心得を思い起こした。それは、お寺に住まいする者にとって大切なことを順々に説くものである。
五か条あって順番に、一に早起き。二に掃除、三にお勤め、四に勉強、最後に法話だったと記憶する。
先師が教えるのは、聞法とは生活の一部の作業というようなものではなく、生活を基礎づけ、その人の生活全体の表現に直結する営みであるということだ。
冒頭に述べた「町たんけん」授業の後、小学生たちからお礼の手紙を受け取った。その一つには次のように書かれていた。
お寺を見せてくれてありがとうございます。お寺に鐘や畑があるなんてびっくりしました。これからもお寺の先生(阿弥陀さま)のため、そうじをがんばってください。ぼくもいつか手伝いにいきます。
授業の最後、小学生たちは、お寺の鐘を一人ずつ撞いた。そのどれもが、素直でまっすぐな響きで思わず合掌。ピカピカの子どもたちのおかげで、あらためて聞法の原点に還らせてもらいつつ、一期一会の出遇いを味わわせていただいている。
(聖台寺 澁谷真明住職)