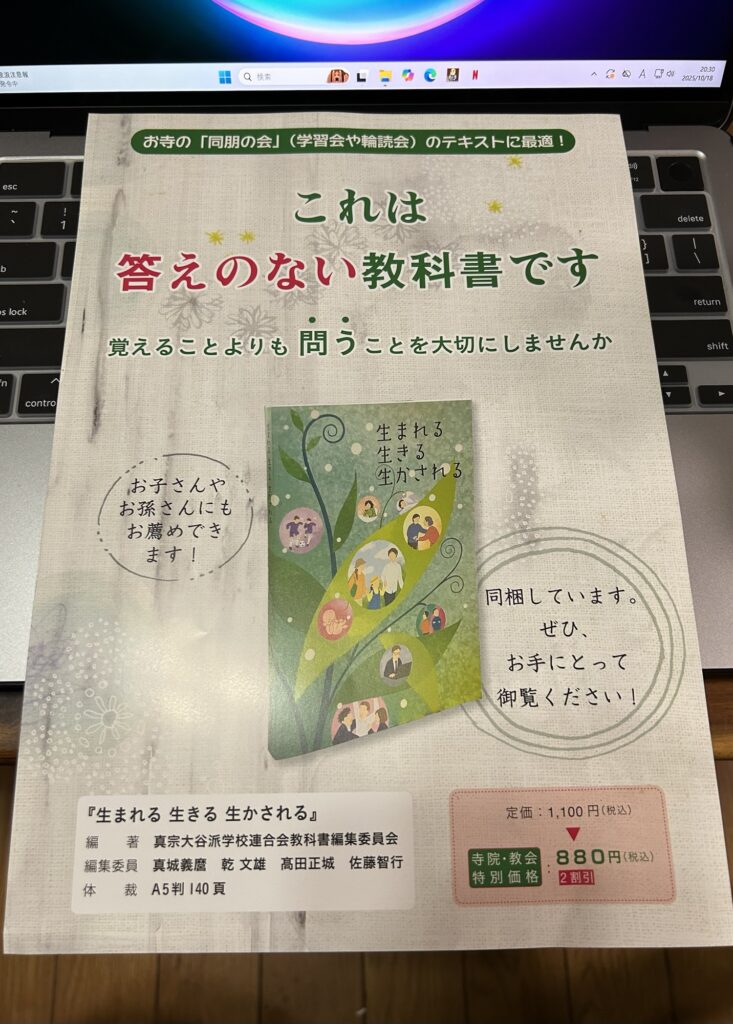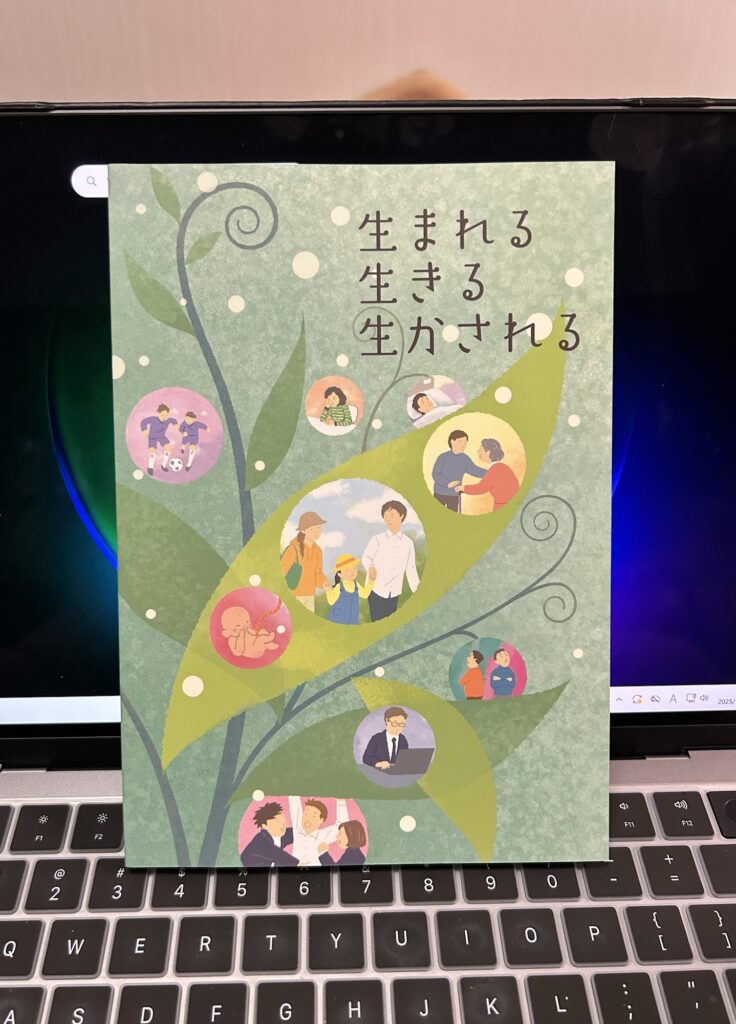ノーベル賞 医学生理学賞を受賞した、京都大学 特別教授 本庶佑さんは、
「研究というのは何か知りたいという好奇心なので、簡単には信じない。教科書に書いてあることは信じない。本当はどうなっているか?山のようにある情報の中で、自分の目で物を見て、自分で確かめる“疑う事の大切さ”」
を、仰っています。
疑う事の大切さとは、
本当の問いを持つことだと思います。
親鸞聖人も、
「念仏は、浄土という世界に往くための原因なのか、また地獄という世界に堕ちる行為なのか、私はまったくわかりません」とおっしゃっています。
え〜!うっそ〜!と思うくらいびっくりするような言葉ですが、
「そもそも宗教、ことに仏教とは、「生きるとは何か」「人間とは何か」という人間存在の問いを深めていくもので、これこそ人間の根源的問いであり、究極的課題です。つまり、答えを出して誤魔化すのではなく、問いこそを大切にし、苦悩する人間に寄り添ってきたのです。答えを与える宗教は、むしろ人間を縛っていくものにすぎないのです。また、人間を問うはずの宗教が、人間の欲望に利用される宗教に転落していってしまっている現状は、至るところで見受けられます。
問いに生きた親鸞聖人の姿勢には、人間を見つめることを忘れて、他にふりまわされながら生きざるを得ない現代に生きる私たちにとって、かけがえのない尊い自分に帰っていく道すじが示されているように思います。
それは、けっして他にふりまわされない人間になることではありません。むしろ他にふりまわされながら生きざるを得ないなかに、それを問い返す眼、執着しない生き方が与えられてくるのだと思います。」(本多雅人)
わかったつもりになり、答えが独り歩きして、問いを持たない自分の生活が言い当てられます。生きるって不思議だなあと問いを持つと明るくなり、答えを握りしめると暗くなるのです。それを仏教では無明といいます。