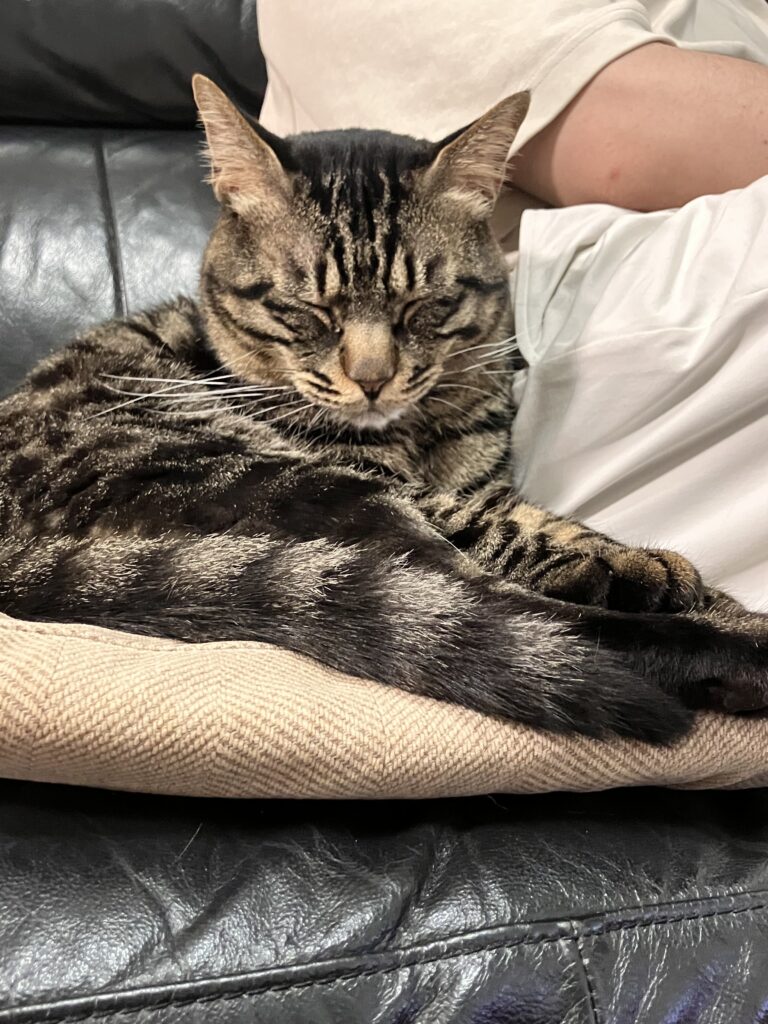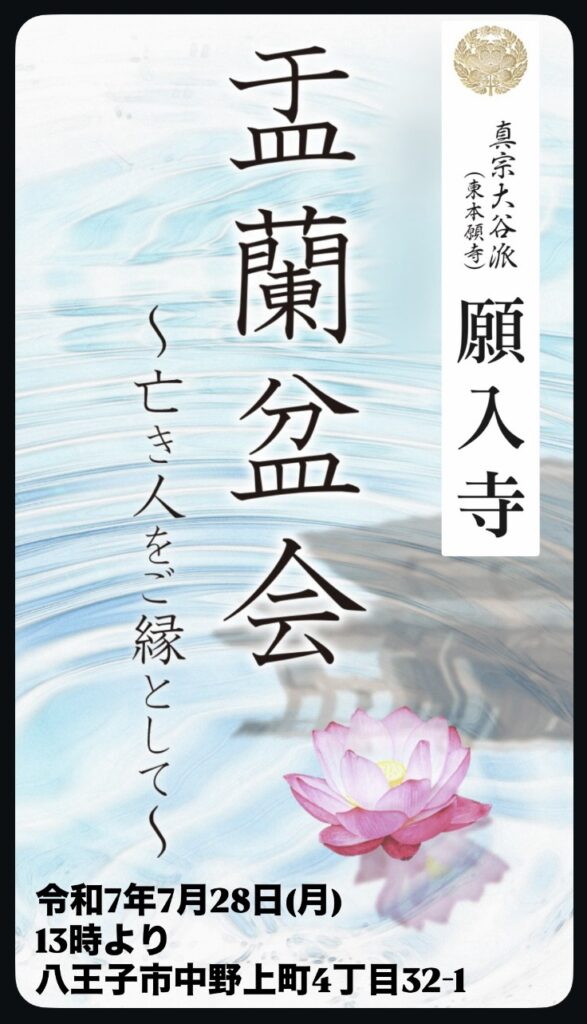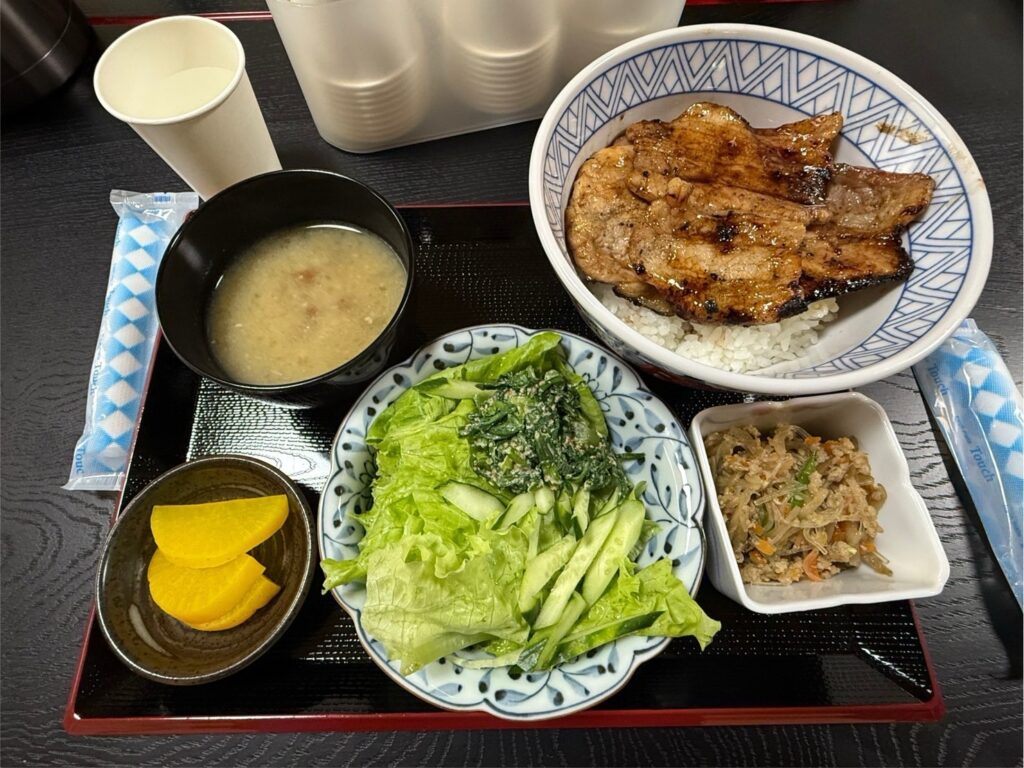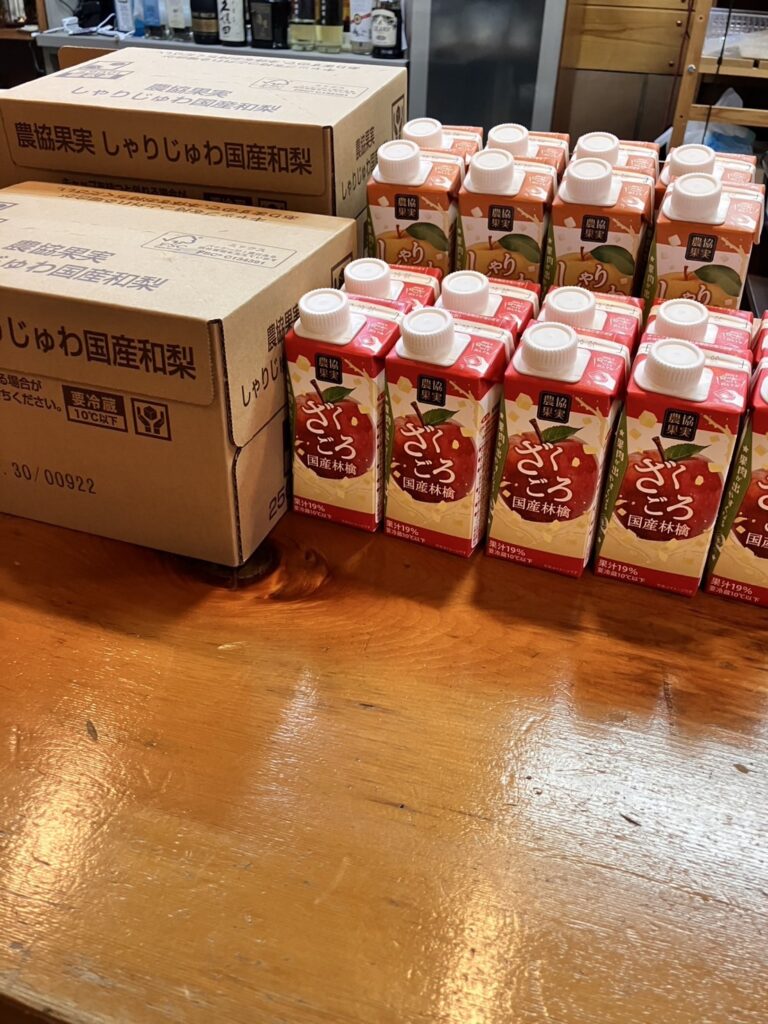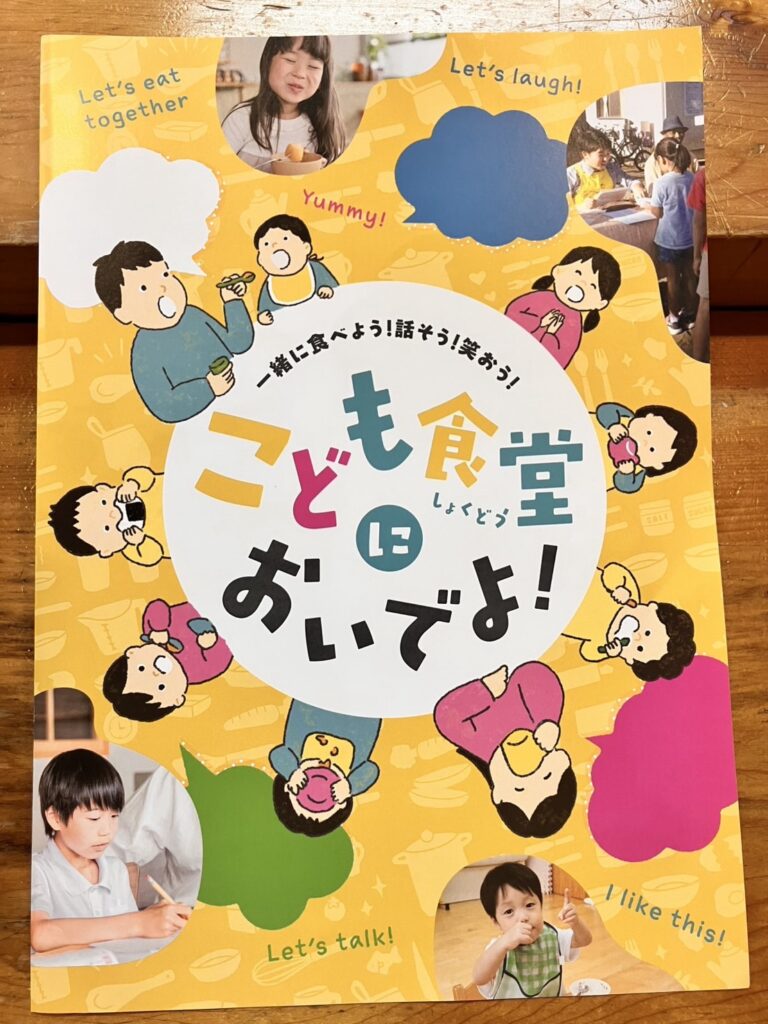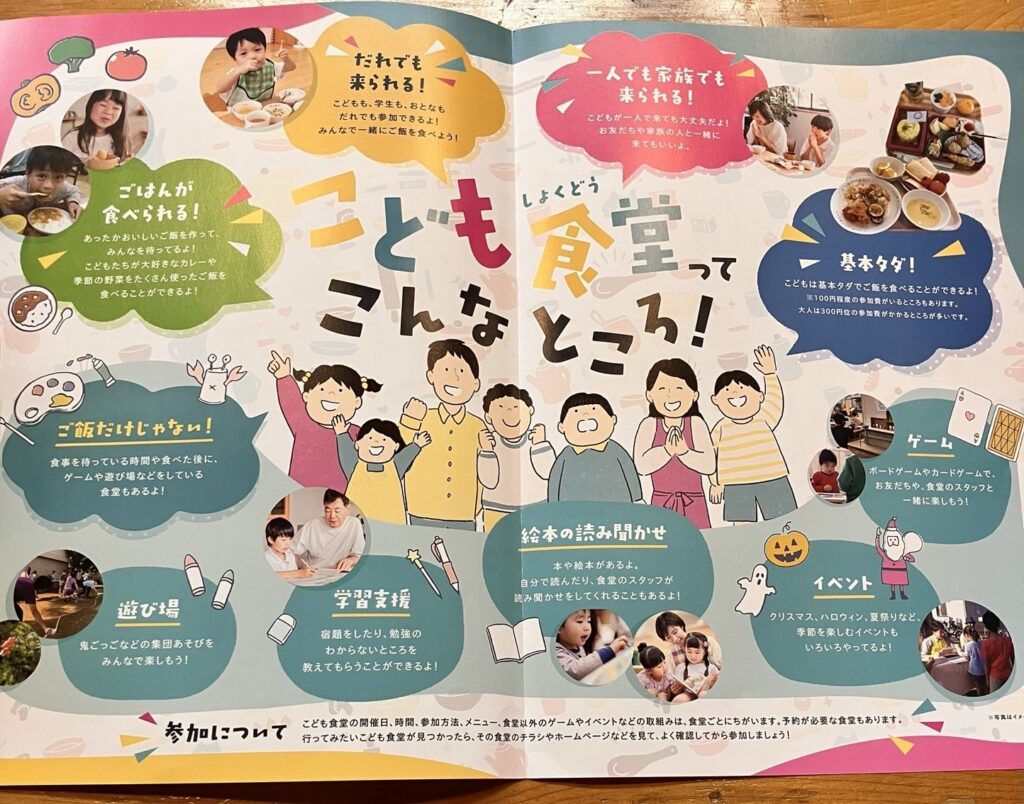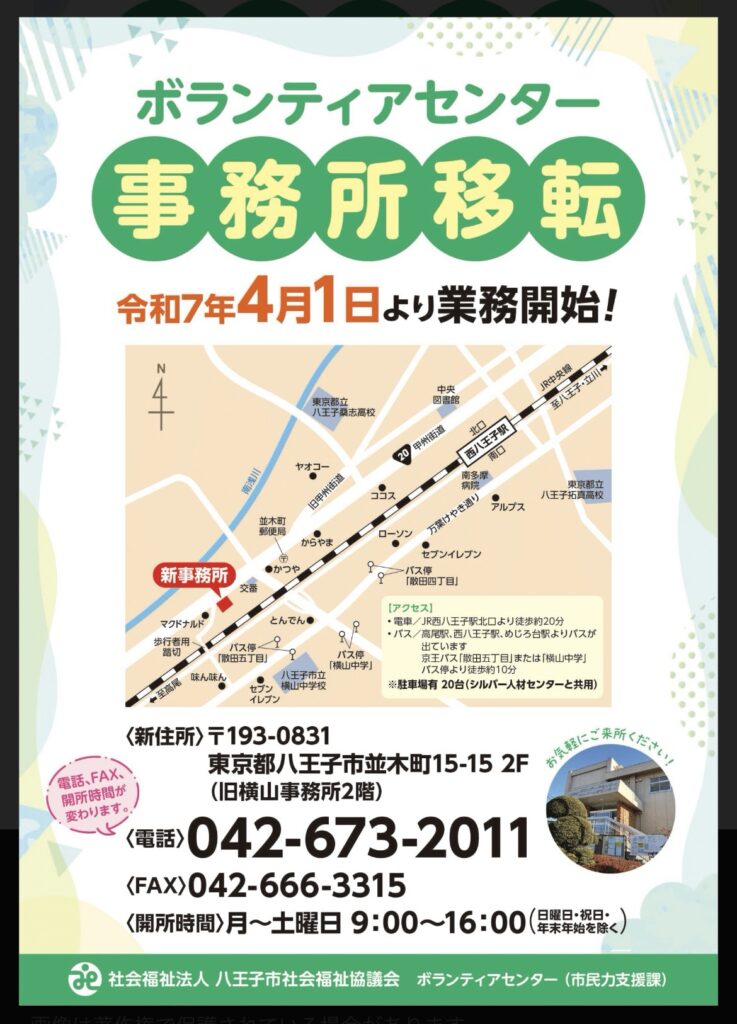思い通りにせずにはおかないという思いが苦しい。
思い通りになっても悩むし、思い通りにいかなくても悩む。
お金があっても悩むし、無くても悩む。
健康でも悩むし、病気でも悩む。
食べても悩むし、食べなくても悩む。
猫に悩みはあるのかな。
悩みが無くなったら、何を頼りにして生きていけば良いかわからなくなるから、悩みは恵み。
知識を身につけた賢い大人が悩み苦しみ迷っている。
「先日、火の玉を見た」と妻が言った。
猫は、火の玉を見ても何も思わないであろう。
「火の玉」は怖いというイメージに悩まされているのである。
火の玉ではなく、蛍の光かもしれない。
漢字の意味を覚えれば覚えるほど、自分勝手なイメージによって迷う。
人は言葉によって迷う。しかし、言葉によって目覚める。迷っていることに目覚める。
こんな私を助けてください。お願いします。
南無阿弥陀仏