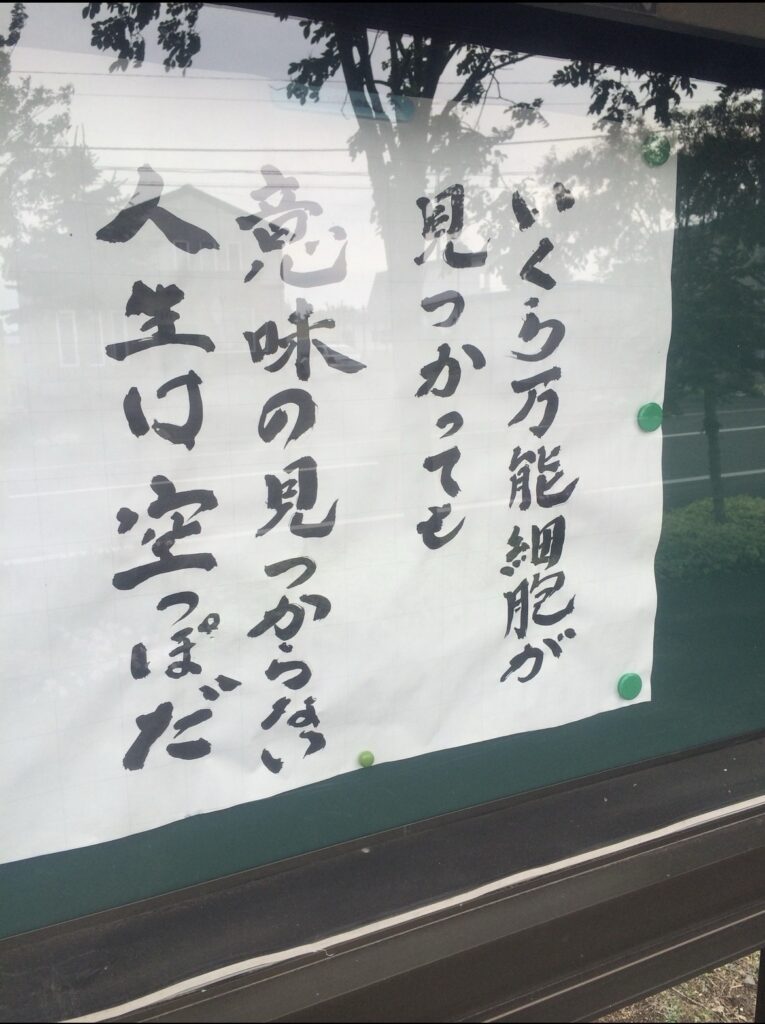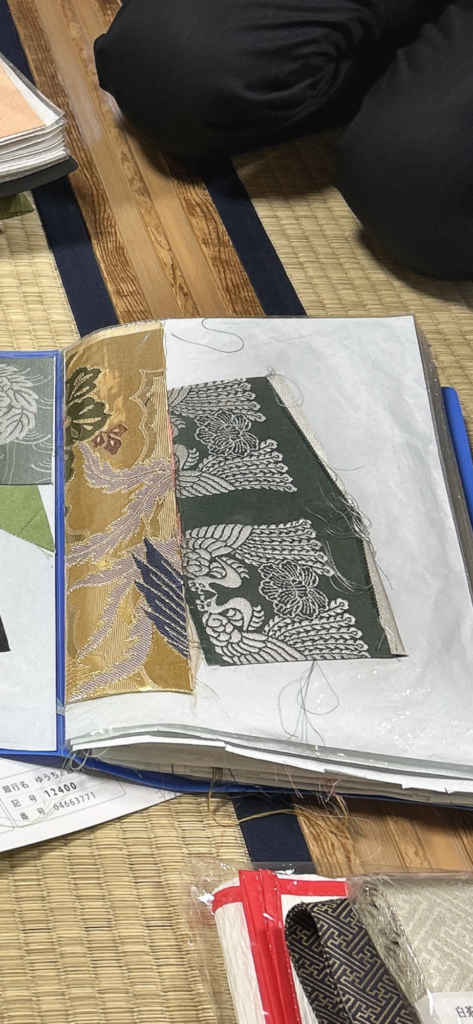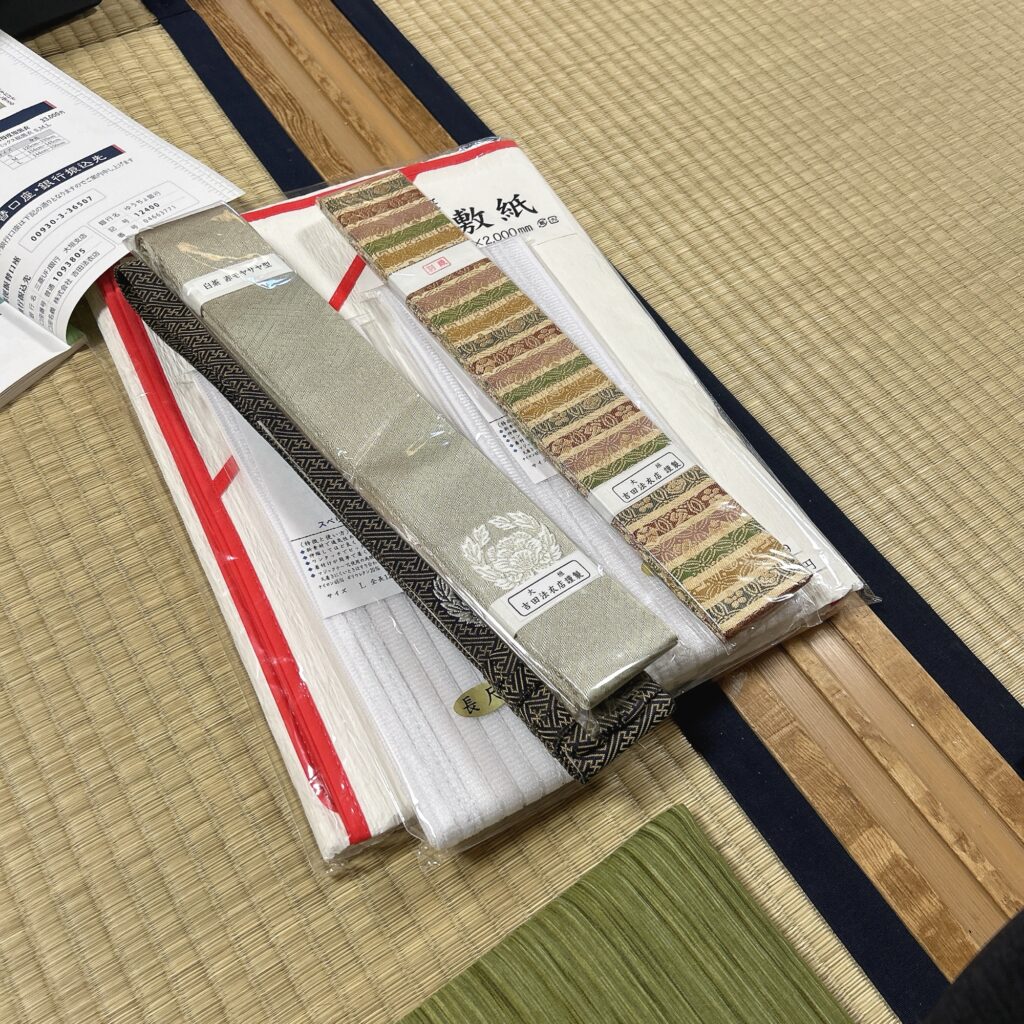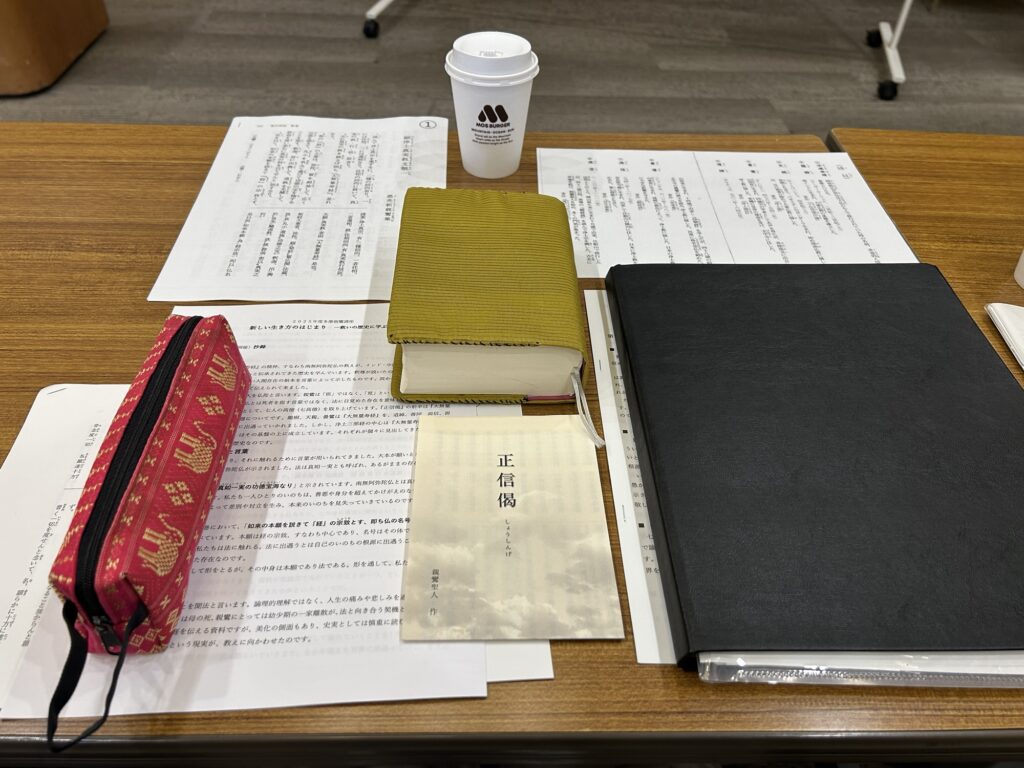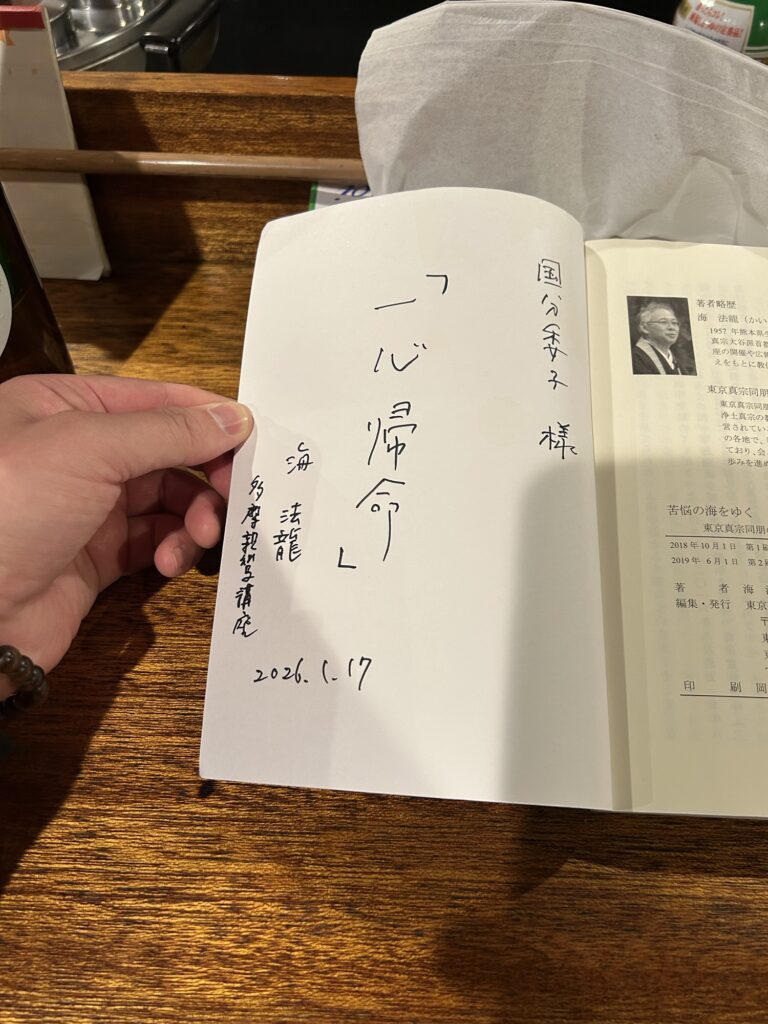教行信証の総序の捨穢欣浄(しゃえごんじょう)。穢を捨て浄を欣いです。穢を捨てとは、嫌なことはできるだけ避けて、これからの人生楽に幸せに生きて生きたいという思いです。そういう生活はいきいきしてこない。なぜなら、その思いは長続きしなく破れ崩れるからです。そういう問題が捨穢欣浄。それが総序にあるという事は、総じていえば、そういう思いが人間の生活の上に起きてきたら必ず、穢を捨て浄を欣うということがある。つまり、生きる事が嫌になったなあという思いは、この身を生きることが喜べないし、楽しめない、いきいきしてこないという問題を捨穢欣浄だと。総ということは普通ということ。普通ということは、普くどんな人にもそういう思いが通じていくということを総という。つまり、どんな人にも通じていくと、誰もが持っているそういう宗教心、そういう現実逃避の思いを表した時に、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という表現をされた。総は、普くですからいつの時代にでも誰にでも起こってくる心ということです。その時その時の気分でも、生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなと。いきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)です。
そして、それに対して教行信証の別序では、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)となっています。総序の捨てるに対して、別序は厭うになっています。
「浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類」p210
これはこれからではなくて今、生きているという今の問題。厭うという意味は、抑えるとか、覆うという意味があります。穢域ということは穢士ですから、世間のことです。世間から押しつぶされそうになっている、抑えられて、覆われている世を世として、見出すことのできた、悲しさとか、辛さ、そういう心が厭うと。世を厭うということは世を批評して捨てたり、批判して排除したりということではなく、悲しさや辛さ、そういう世の悲しさや辛さに寄り添う心が厭うだと。それが、別序に出てくるということは、別というのは特別という意味ではなくて、独自ということ。私一人においてということ。教行信証の別序でいえば、親聖人においてということ。総はすべての人ということで、別は自分においてということだと。
世にあってこの身を生きているその私一人においてはどういうことかといったら、浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類というふうにおさえられています。つまり、浄邦を欣う徒衆、徒衆という私一人において確認することができたということ。つまり、普通の世間一般的な宗教心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心よりももっと深い宗教心という欣浄厭穢(ごんじょうえんね)という心があるんだと。世のなか生きるのがしんどいとか、どっか別に楽しい場所はないかなと言っている思いの底に浄土を厭うという事を通して、穢域を捨てるのではなくて厭うという事があるんだと。それが私一人において確認されたということが別だと。
生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなという思いは僕にもあります。そして、そういう生活はいきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじよう)であるということは、総序で言えば、いつの時代にでも誰にでも起こってくるそういう思いはあるけれども、世を生きているということが、どっかで気になったという心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心からまず出発する。
観経で言えばイダイケの愚痴です。その場面を厭苦縁と言います。いだいけが愚痴を言う場面です。そして、そういう思い愚痴を超えて、娑婆を捨ててどっか別な場所を願うのではなくて、別序で言えば、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)。観経で言えば、欣浄縁です。阿弥陀仏のみもとに生れたいと願う場面です。穢土を捨てるのではなくて、厭うんだと。念仏申す人々は世を厭うんだと。
捨てるのではないと。世から逃げ出すのではないと。つまり、世を穢域として厭う。捨てるというのは気分の問題で厭うということは浄土から見出されたはたらきを浄邦ということです。
そして、それに対して教行信証の別序では、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)となっています。総序の捨てるに対して、別序は厭うになっています。
「浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類」p210
これはこれからではなくて今、生きているという今の問題です。厭うという意味は、抑えるとか、覆うという意味があります。穢域ということは穢士ですから、世間のことです。世間から押しつぶされそうになっている、抑えられて、覆われている世を世として、見出すことのできた、かなしさとか、辛さ、そういう心が厭うと。世を厭うということは世を批評して捨てたり、批判して排除したりということではなく、悲しさや辛さ、そういう世の悲しさや辛さに寄り添う心が厭うだと。それが、別序に出てくるということは、別というのは特別という意味ではなくて、独自ということ。私一人においてということ。教行信証の別序でいえば、親聖人においてということだと。総はすべての人ということで、別は自分においてということだと。
世にあってこの身を生きているその私一人においてはどういうことかといったら、浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類というふうにおさえられています。つまり、浄邦を欣う徒衆、徒衆という私一人において確認することができたということ。つまり、普通の世間一般的な宗教心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心よりももっと深い宗教心という欣浄厭穢(ごんじょうえんね)という心があるんだと。世のなか生きるのがしんどいとか、どっか別に楽しい場所はないかなと言っている思いの底に浄土を厭うという事を通して、穢域を捨てるのではなくて厭うという事があるんだと。それが私一人において確認されたということが別だと。
生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなという思いは僕にもあります。そして、そういう生活はいきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじよう)であるということは、総序で言えば、いつの時代にでも誰にでも起こってくるそういう思いはあるけれども、世を生きているということが、どっかで気になったという心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心からまず出発する。
観経で言えばイダイケの愚痴です。その場面を厭苦縁と言います。いだいけが愚痴を言う場面です。そして、そういう思い愚痴を超えて、娑婆を捨ててどっか別な場所を願うのではなくて、別序で言えば、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)。観経で言えば、欣浄縁です。阿弥陀仏のみもとに生れたいと願う場面です。穢土を捨てるのではなくて、厭うんだと。念仏申す人々は世を厭うんだと。
捨てるのではないと。世から逃げ出すのではないと。つまり、世を穢域として厭う。捨てるというのは気分の問題で厭うということは浄土から見出されたはたらきを浄邦ということです。