インドカレー🇮🇳
ご飯がシラスみたいですね🤔
スプーン🥄がない。
手で食べろってことかな😹
新宿で30年やってるお店だそうですが…
めっちゃ辛かった🫢
ご馳走さまでした🙏
南無阿弥陀仏

住職の独り言ささやきです。親鸞聖人は小さなつぶやきやささやきに耳を傾けて人々の言葉を聞き逃さなかった方だと思います。
インドカレー🇮🇳
ご飯がシラスみたいですね🤔
スプーン🥄がない。
手で食べろってことかな😹
新宿で30年やってるお店だそうですが…
めっちゃ辛かった🫢
ご馳走さまでした🙏
南無阿弥陀仏

南インド🇮🇳の方がお参りに来てくださいました🙏😌✨
クリスチャンだそうです
南無阿弥陀仏

いただきました。
南無阿弥陀仏


絵は妻に任せてます😹
南無阿弥陀仏

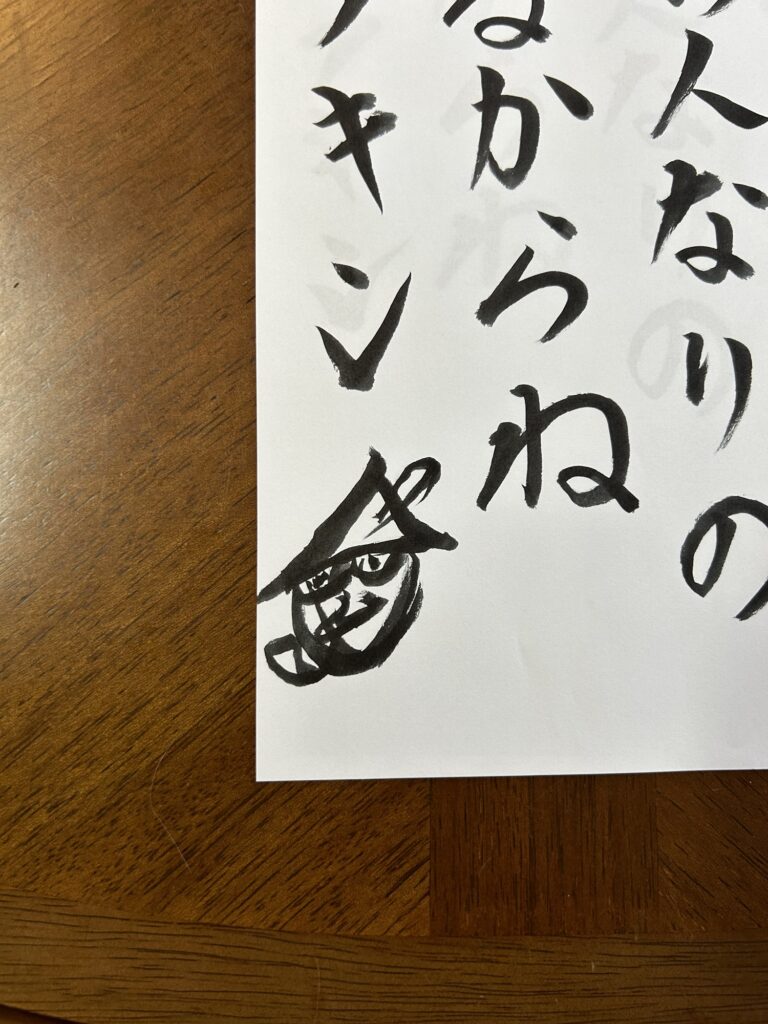
恩師の言葉
「政治であっても宗教的な情報を自由にはできません。問い合わせがあってもはっきり断ればいいです。
これは大谷派全体の方針です。」
南無阿弥陀仏

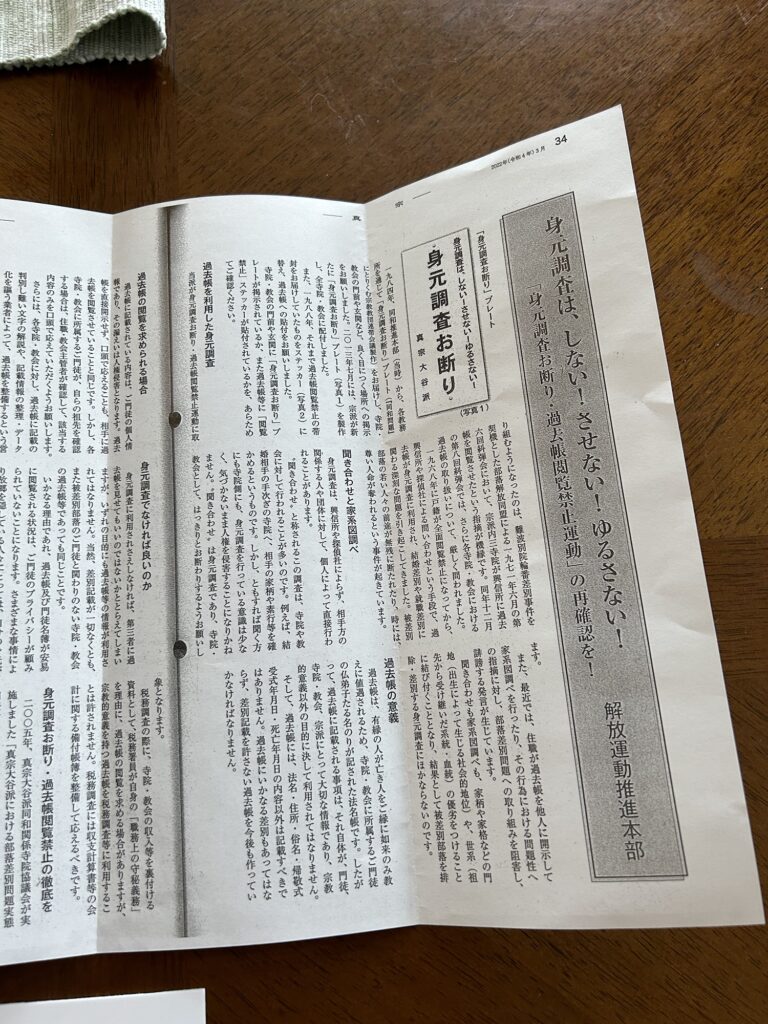

場所作らなきゃ🥹
あとは仏教書とマンガ💡
南無阿弥陀仏

南無阿弥陀仏

仕入れに行き、並べてみました。
まだまだ改善の余地はあります。
少しずつ形にして行きたいと思います。
南無阿弥陀仏




屋根2日目。
今日は帰宅後、よし、僕も足場を使って登ってみようと思い、
脚立で挑戦。
体重制限があるのか、ゆらゆら危ない…
登れたけど降りられるかな…
絶対登らない方がいいです⚠️
南無阿弥陀仏



昨日は飲食店で、隣りに座った男性が引退したご近所の大工さんだった。
「お寺さんは立派な職業だ」
では、交代してくださいと言いました。
大工さんだって立派なお仕事。
その方は、大工は大きく工夫するから大工なんだと力説されておりました。
なるほどです。
僕は工夫してるだろうか?
大きくても小さくても、何かを工夫しなければ、クリエイティブでは無くなってしまう。
南無阿弥陀仏