







近所の人たちがお地蔵さんを見に集まってきた。
ある一人の方が、
「これじゃあ、覗き地蔵だ」
と言うので、みんなで真ん中のお厨子をひっくり返して見えるようにしていただき拝んでくれた。
南無阿弥陀仏









恐れと罪の問題を抱えて、苦しみながら生きている我々は、地蔵菩薩とか観世音菩薩とかの菩薩たちに親しみを感じながら生きてもいる。地蔵菩薩のことを大悲闡堤(だいひせんだい)ともいう。闡堤とは仏法を否定する者のことで、仏(ぶつ)に成る、その仏種(ぶっしゅ)・仏性(ぶっしょう)が腐っているため、永遠に助からない者とされている。しかし地蔵菩薩は、この世の中で苦しんでいる者がいる限り、その者を見捨てないでその苦しみを共にして、共に助かっていこうと大悲心の故に敢えて助からない者となっていくのである。そのことから大悲闡堤と呼ばれている。
また観世音菩薩のことを施無畏者(せむいしゃ)ともいう。世の中に恐れをもって生きている者があれば、その者の恐れを取り除いて、無畏の心を施すことによってその者を助けようとする。そのことから施無畏者と呼ばれている。
宮沢賢治に「雨ニモ負ケズ」の詩があるが、そこで賢治は
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
としながら、さらに
東ニ病気ノコドモアレバ
行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ
行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ
南ニ死ニソウナ人アレバ
行ッテコハガラナクテモイゝトイヒ
と続けているが、そこには観世音菩薩とか、地蔵菩薩とかに等しい菩薩の精神がよく示されている。
実は菩薩とは、「大慈悲心こそが真実である」として、自分も大慈悲心を学び、行ずることによって仏に成ろうと願いを立て、その願いに生きている者のことである。龍樹(りゅうじゅ)は、「世に四種の人あり」として、一、自利のみの人。二、利他のみの人。三、共利(ぐり)の人。四、不共利(ふぐり)の人を問題としている。我々は社会的存在として、縁のある人とお互いに関係しあいながら生きている。その時、お互いの関係はどうなっているのかがいつでも問題になるだろう。
一、の自利のみの人は、いつでも自分の都合を第一に考えながら生きていて、その都度、他人を犠牲にしている者のことである。そのため犠牲になっている人が事実いるため、本当にこれでよしと満足することができない人のことである。
二、の利他のみの人とは、自利のみの人とは逆に、他人のことを第一に考えながら自分を犠牲にして生きている者のことである。しかし自分が犠牲になっているという思いがあるため、やはり本当にこれでよしと満足することができない人のことである。
三、の共利の人とは、真実とは何か、そのことを第一に考えながら、その真実にしたがって生きることによって、他人を犠牲にするのでもなく、自分を犠牲にするのでもなく、自分も他人も共に助かっていくことができ、自利利他円満の生き方の出来る人のことである。仏とは、共利の人のことであり、自利利他円満に生きられる人のことである。それは真実そのものである大慈悲心によって初めて成就することになるから、仏のことを満足大悲の人ともいう。本当にこれでよしと満足することの出来ていく人のことである。
我々が仏の弟子となるというのは、そのような仏の弟子となって、仏の大慈悲心を学び、それをよく行ずる者となっていこうと願いを立てることである。皆の中にはすでに得度(とくど)を済ませている人もあるし、これから得度をする人もいると思う。得度とは、伝統的には善知識(よき人)より頂髪剃頌(ちょうはつていじゅ)といわれる
流転三界中 恩愛不能断 棄恩入無為 真実報恩者
(三界の中を流転して 恩愛断つことあたわず 恩を棄て無為に入り 真実に報いる者となれ)
によって願いをかけられながら頭を剃ってもらい、さらに
帰依仏 帰依法 帰依僧
と誓いを立てて僧になり、法名 釋の名になり、法名 釋◯◯を名告ることである。このことこそ我々が仏弟子となることなのであり、菩薩たちの仲間入りをすることである。このことを原点として我々は仏に成ろうとする仏弟子としての菩薩の歩みを始める。その時には、必ずいつでも自分の都合を第一と考えてしまう根深い恩愛(おんない)の心を思い知らされ、その心との死闘の中で仏弟子としての菩薩の歩みが展開することになる。念仏との出遇いは、その死闘の末にある。
《平成6年(1994年)4月25日》
2,自力作善の人
大谷専修学院 竹中智秀院長 【歎異抄講義】④
三章においては、善人・悪人が問題となっていて、その善人について「自力作善(じりきさぜん)の人」と言われている。誰でも仏弟子となって、仏の教えにより成仏道を歩みはじめると、まず仏の、しなければならない善、してはならない悪として説き示される諸善をおこない、廃悪修善(はいあくしゅぜん)をしはじめる。
その時、諸善の根本になるのは、慈心不殺(じしんふせつ)である。命あるものは、どのようなものでも、そのものを尊び、愛そうとする人には心を開いてつき従おうとする。しかし逆に、軽蔑し傷つけようとする人には心を閉ざしてつき従おうとはしない。それは命そのものの宿している法則である。このことは我々自身が十分によく知っている。後序で、聖人の問題とされている「如来の御心によしとおぼしめす善、悪しとおぼしめす悪」とは、このことを言うのであって、実は我々もよく知っている事である。
しかし、いざ思い立って慈心不殺しようとおこない始めると、そのことの困難さを思い知らされる。自力作善の人は、このことを誠実におこなおうとし続ける人のことである。実は成仏道とは、我々の業(=おこない)に関わる問題である。その業は、身業(しんごう)、口業(くごう)、意業(いごう)の三業でもって表され、「業の体(たい)は思(し)なり」として、特に意業が重視される。しかも思も三思(さんし)として、一、審慮思(しんりょし)。二、決定思(けつじょうし)。三、発動思(はつどうし)と徹底して問題にされている。
一、の審慮思とは、あれかこれかと思案をつくして選択していくことである。二、の決定思とは、あれではない、これだと決定することである。三、の発動思とは、決定したことをそのまま実行することである。このように業の体が思であることによって、業は自由を表し、それと同時に自由であるからこそ責任を表すことになっている。このことは、業は“牽く”とも言われていて、業をなすことによって将来の身と境遇が約束され、与えられてくる。それが責任を引き受けることである。業と言えば、何か暗い、運命的なものを感じがちだが、そうではない。この業(=おこない)の自由と責任ということの確認を前提として、深信因果(じんしんいんが)、自業自得(じごうじとく)ということが成り立ち、仏道が始まる。
しかし因果を問題にする時、一、等流因果(とうるいんが)。二、異熟因果(いじゅくいんが)との、二種の因果のちがいをよく知っておくべきである。一、の等流因果とは、善因善果(ぜんいんぜんか)、悪因悪果(あくいんあっか)のことである。善は善に等流し、悪は悪に等流するという因果を言う。一旦はじめにおいて悪であったものは、永遠に悪であり続けることになってしまう。世間で言う因果は、この等流因果を言っていることが多い。そのため多くの問題を引きおこしている。
二、の異熟因果とは、善因楽果(ぜんいんらっか)、悪因苦果(あくいんくか)のことである。楽とか苦とかは、善でも悪でもなく無記(むき)と言われ、業とはならない。因と果が同質ではなく、異熟として熟した。そのため異熟因果といわれる。この異熟因果の因是善悪(いんはこれぜんまく)、果是無記(かはこれむき)を鉄則として、仏道は三世両重(さんぜりょうじゅう)の因果によっておこなわれてきている。それは過去(前世)と現在(げんせ)とは因果の関係。現在(現世)と未来(来世)とは因果の関係を言う。だから因是善悪と、いつでも今が成り立ち、廃悪修善をはじめていくことになる。
もし等流因果であれば、善は善、悪は悪に等流するため、因是善悪として廃悪修善をはじめていくことができない。思い立って慈心不殺しようとおこない、その都度そのようにできないで、そのことを苦とするからこそ、繰り返し「だからこそ」だと慈心不殺しようとはじめていけるのは、異熟因果を深信するからである。
その自力作善の人を、世間の人は、他力をたのむ悪人と比べて、善人として評価している。しかし聖人は、その自力作善の人を、念仏申すようになったのだが、念仏が信じ切れないで疑いをもっている「疑心の善人」とされ、報土の往生をとげることはできないと批判されている。
このことは、自力作善の人は、まず、一、自分自身に対して何事も心に任せて思いのままにできる身であると妄想していて、慈心不殺がてきていない自分自身の身の事実が見極められていないのである。さらに、二、なぜ慈心不殺ができないのか、それは自分自身が「さるべき業縁のもよおさば、いかなるふるまいもすべき」煩悩具足の凡夫の身であるという、その道理が見極められていないからである。この問題は、誰にでも共通する問題であって、そのことが曖昧なために、念仏を疑うという問題が起きているのである。
《平成6年(1994年)5月9日》
3,時機相応の教としての念仏
大谷専修学院 竹中智秀院長 【歎異抄講義】⑤
仏弟子として、自利利他円満を願って生きていこうとする時、因是善悪、果是無記とする異熟因果に依ることを見てきた。だからいつでも“今”に立って、仏弟子として生きていこうと決意した、その初めに立ち返って、問題があればあるほど、だからこそだと廃悪修善していけばよい。
誠実にそのようにしている人々がある。しかし聖人は、そのような人々のことを「自力作善の人」として問題にされている。何故なのか。このことは、聖人自身もかつて自力作善の人として誠実にそうされる中で思い知らされたことがある。それは「教」と「時」と「機」の問題である。聖人はこの問題について、
信(まこと)に知りぬ、聖道の諸教は、在世正法のためにして、まったく像末・法滅の時機にあらず。すでに時を失し機に乖(そむ)けるなり。 (「教行信証」化身土巻)
と言い切られている。
我々は皆、いつかどこかの誰かとして生きているのではなく、いつでもない今、どこでもないここ、誰でもない私自身として、今・ここという、時代的にも社会的にも限定を受けて生きている存在である。それを時機的存在という。その時機的な存在であることを見極められないと、我々は単なる個人として、何でもできるような幻想に取りつかれてしまう。
諸善を中心とした廃悪修善の教えは、聖道自力の教えで、正法の時機においては意味を持つ。しかし末法の時機においては、我々の成仏道をかなえる教えとはならない。聖人は自分自身の身の事実を通して、末法の時機であることを見極められている。そのことによって時機相応の教としての念仏に出遇われた。
特にその末法の時機を「五濁(ごじょく)の世」として、それは
① 五濁増のしるしには
この世の道俗ことごとく
外儀は仏教のすがたにて
内心外道を帰敬せり (「正像末和讃・悲嘆述懐讃7」)
② 五濁邪悪のしるしには
僧ぞ法師という御名を
奴婢僕使となづけてぞ
いやしきものとさだめたる (「正像末和讃・悲嘆述懐讃12」)
として見切られている。「しるし」とは、その事実を見れば、末法が何であり五濁が何であるか分かるということである。
「この世の道俗みなともに」と、「道」とは出家者・僧であり法師である。「俗」は在家者である。その俗も僧も皆が、外から見た目には仏教を尊んでいるように見えるのだが、内心は外道に帰依して、僧も俗もそれぞれが、仏教すら利用して、吉凶禍福に迷うて我が身一人の利益を第一に考えている事実がある。
また「僧ぞ法師という御名を」と仏弟子を示す、僧とか法師とかの尊い名が、奴婢(ぬひ)とか、僕使(ぼくし)とかを呼ぶ名として用いられていて、そのことを当の法師もあたりまえのようにしている。そういう事実によって、お互いに僧とか法師とかを軽蔑し、差別している事実がある。そういう事実こそが、末法五濁の世となっている「しるし」である。聖人は、そのしるしを「目ある者は見よ」と叫ばれている。このことは末法万年ともいわれる現代においても同じことである。そのしるしが我々にも見切られているだろうか。
また聖人は、仲間の聖光房が、法然上人より「あなたは髻(もとどり)が切れていない」と批判された時、聖光房が「私は出家得度して何年にもなっている。どうしてそのように言われるのか」と問い返したのに答えて、「法師には三つの髻がある。それは勝他(しょうた)・名聞(みょうもん)・利養(りよう)である。この三つの髻を剃り捨てなければ法師とは言えない」と教えられている。その教えを親鸞聖人は、自分自身の教えとして受け止め、いつもその教えを思い起こされている。(「口伝鈔」9)
そういう勝他・名聞・利養の心の根強い我が身を、結局は煩悩具足の凡夫としての我が身を、生涯をとおして深められてもいる。聖人はそのように、一、末法五濁の世を見極め、二、煩悩具足の凡夫の身を思い知らされて生き抜かれている。
しかしまた一面、自利利他円満の仏の大悲を聞けば、それこそ真実だ、とうなづけるのも事実であり、また「命はそれを愛する者につき従う」と聞けば、やはりそれも真実だ、とうなづけるのも事実である。だからこそ、その真実にしたがって成仏道の願いをなんとしても実現したいと願われている。「その願いをかなえさす教えこそが念仏である」と 決着し、我々にも勧められているのである。
《平成6年(1994年)5月16日》
4,念仏者=他力をたのみたてまつる悪人
大谷専修学院 竹中智秀院長 【歎異抄講義】⑥
五濁悪世のしるしは、仏教といっても、その仏教が外儀は仏教、内心は外道となっていることにある。それは仏教が、我々自身の名利心(みょうりしん=名聞・利養の心)のために利用されていることにある。このことは我々が煩悩具足の凡夫以外の何者でもないことを示す、そのしるしでもある。しかしその五濁悪世こそ、阿弥陀如来の誓願が広まり、念仏往生が盛んとなる時でもある。なぜなら如来の誓願は、凡夫の身を生きる他のない我々を助けようと起こされているからである。
その誓願は、
たもちやすく、となえやすき名号を案じいだしたまいて、この名字をとなえんものを、むかえとらんと、御約束あることなれば(「歎異抄」十一章)
とある。如来は念仏申すものを如来自身が、その、えらばず・きらわず・みすてずの大慈悲心をもって統治する国(真実報土)へ迎えとろうという誓願を立てて我々を助けようとされている。聖人はその誓願に助けられた。だからこそ我々に念仏を勧められている。問題は、我々がその勧めを聞いて、如来の誓願を信じ念仏申す身となれるかどうかである。
そのためには、一、世間の人たちが、我々が仏法を利用しているといって軽蔑しようとも、それを問題にするのではなく、また、二、我々自身が仏法を利用していることを知り、自己嫌悪に陥ることがあっても、それを問題にするのではなく、三、「ただひたすら如来の誓願を信じて、念仏申す身となれ」と勧められる聖人の声を聞き、四、「我が名を称する者を迎えとらん」と呼びかける如来の声を聞き、それを信ずるのである。
浄土真宗の伝統は、信心為本(しんじんいほん)にある。よく「如来の国はどこにあるのか」と云々されるが、それは如来の誓願を信ずる我々の信心に開かれて、その国は成就する。そのことと無関係にその国がどこかにあるのではない。
世間もまた我々も、いつでもよしあしを云々しては、我々自身をえらび・きらい・みすてることがある。そのため我々は、みずから自身に安らぐことができない。だからこそ如来は、凡夫の身を生きる我々をいつでもそのまま、えらばず・きらわず・みすてず摂取不捨して、我々が自身に安らぐことができるように、如来自身が統治する国を作り上げ、その国に我々を迎えとって助けようと誓願を立てられている。
その誓願を信じ、念仏申す身となって如来に我が身をまかせていけばよい。「我、如来を信ず」と言い切り、南無阿弥陀仏と念仏申す身となれるかなれないか、それがすべてを決する。その時、我々ははじめて凡夫の我が身に安らぐことができる。たとえ外儀は仏教、内心外道として生きていようとも、その身を大事にし、言い訳もせず、正当化もせず、謙虚に生きることがはじまる。そして深く深く生きることになっていく。聖人が「他力をたのみたてまるつ悪人」とされているのは、その念仏者のことである。
南無阿弥陀仏





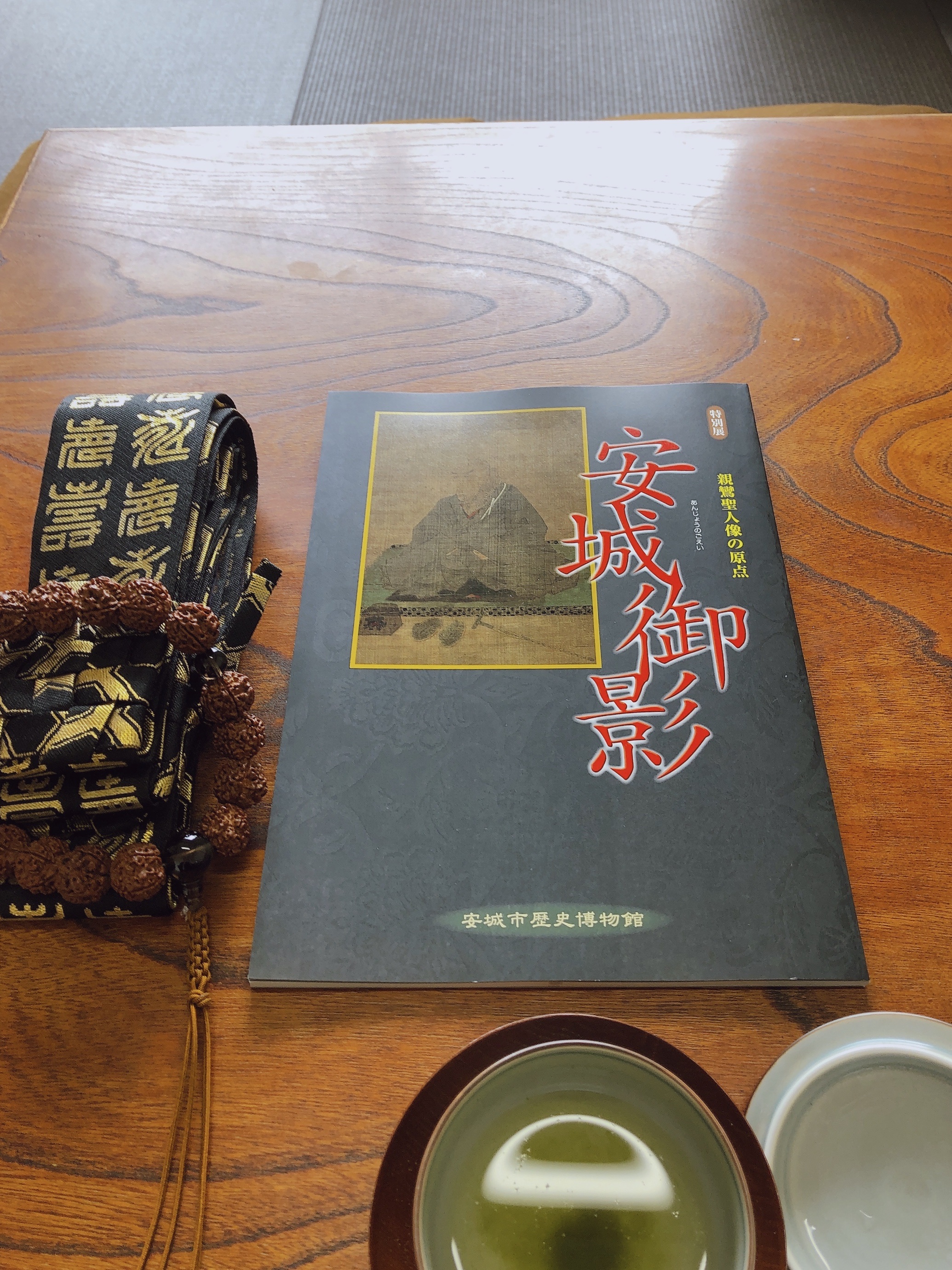
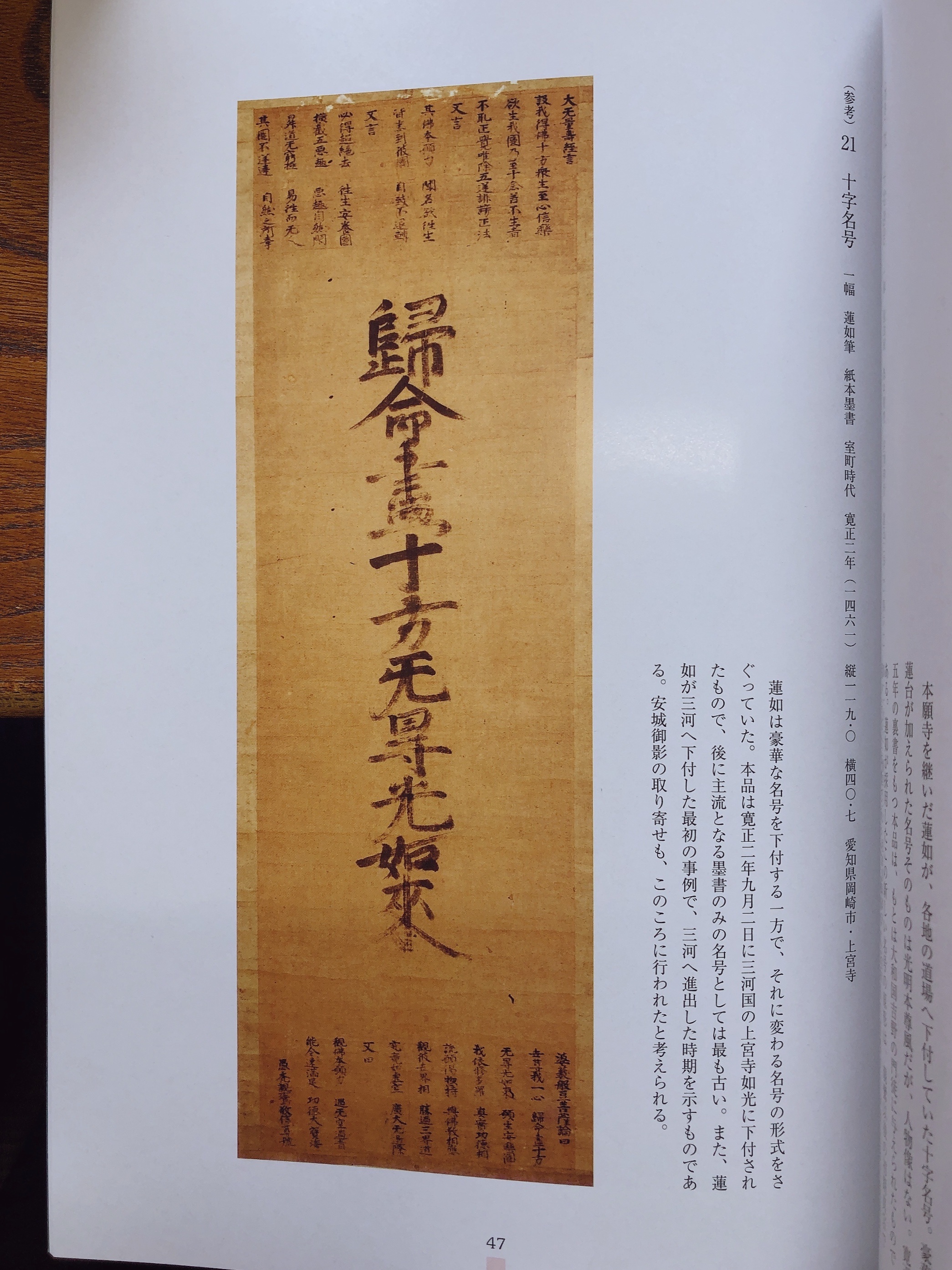

以前から欲しい物だったので、たまたま手に入る事が出来て嬉しいです。




